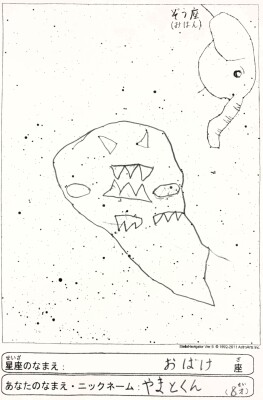スタッフブログ 親子天文教室「望遠鏡を作ろう」

8月31日(日)親子天文教室「望遠鏡を作ろう」が開かれました。毎年定番の人気講座で、中秋の名月や月食などの天文現象にあわせて実施されます。今年は、9月8日:皆既月食、10月6日:中秋の名月、3月3日:皆既月食をねらって、この時期での開催です。ちなみに、2月22日にも同じ講座を計画中ですので、ご希望の方はぜひお申し込みください(*'▽')。

まずは、参加したみなさんに望遠鏡の仕組みやつくり、開発に至った歴史や偉人たちの功績についてご紹介しました。今回の講座は科学センターの学芸員や星のボランティアのみなさんが講師をしています。天体望遠鏡や星空についての詳しいお話を楽しく勉強しました。1つご紹介します。星の位置を空で伝えるのはなかなか難しく、主に角度で表します。指を開いた人差し指と親指の間が15度、握りこぶしが10度、人差し指の指先が2度です。他にも、「実は、中秋の名月の日は満月じゃない(꒪ȏ꒪)エッ?!」とか、「満月の大きさは、日によって違う(꒪ω꒪υ)?!」とか、楽しい話題もたくさんあり、大人の方もほぉ~と興味深く聞いてくれていました。

さあ、いよいよ望遠鏡工作です。最初にして、最難関! 小さなレンズを3枚組み合わせて、接眼部を組み立てます。レンズは、天体望遠鏡でも一番大切な部品です。扱い方次第で、傷や汚れがついて、せっかくの天体が思うように見えません。教えてもらったレンズの正しい触り方:横からフチを持つやり方で慎重に組み立てます…ドキドキ(;´・ω・)
無事、3枚の形が違うレンズを組み合わせて、溝にはめ込み、天体望遠鏡の接眼部分が完成しました。どの子ものぞいて、ちゃんとできたか、汚れがないかチェックします。

次に鏡筒部分、天体望遠鏡の本体を組み立てます。大きなレンズが1枚、実は2枚の形が違うレンズがはり合わされている物で、ガリレオの時代から進化したレンズです。向きに気をつけて、本体につけたら、接眼部分と合体して、おおまかな形ができてきました。
早速、教室の窓から外を眺めて、ピントを合わせてみます。汚れが目立ったり、ピントが合わなかったり、怪しいものは、すぐに星のボランティアのみなさんが点検や修理をしてくれました。無事、みなさん遠くのものが大きくはっきり見える望遠鏡の本体が組み上がりました。
ちなみに、天体望遠鏡で覗いた視野は「鏡像」といって上下左右が逆さまに見えます。中には、壊れた!失敗!ゲッ!(꒪ꇴ꒪|||)と、思った子どもたちも多く、その後のお話を聞いて、ホッと一安心でした。実際の星空を見上げるときには、上下左右の向きを間違えないように、上手に使ってくださいね。

最後に、スキマに遮光テープや三脚用の金具などを取り付けたら完成です。正しい扱い方やピントの合わせ方、見たい星の探し方など、大切なお話を聞いたら、いよいよお試しに屋外へ出かけました。
今回の工作は、手持ちの天体望遠鏡ですが、特別に三脚に取り付けて、どのように見えるか確かめてみました。どの子も自分で作った望遠鏡が、どのように見えるかワクワクです。「山の向こうの鉄塔が見えた」「遠くの看板の字まで見えた!さかさま~」など、完成した望遠鏡の見え方に喜びや感動いっぱいでした(。☉▼☉)ワァオ☆
最後に、講座の中で何度もくり返し注意がありましたが、とても大事なことなので改めてお知らせです。望遠鏡で太陽を絶対に見てはいけません!!くれぐれもご注意ください。
科学センターでは、望遠鏡工作以外にも、天体観望会や天文台公開など、気軽に参加できる天文イベントをたくさん催しています。ホームページにたくさん情報が出ていますので、みなさんぜひご参加ください。
本日参加した子どもたちが、今日作った望遠鏡で皆既月食や他の星座を楽しんでくれることを願っています。参加してくださったみなさん、ありがとうございました。惜しくも、落選したみなさん、2月にまた機会がありますので、ぜひご応募ください。お待ちしています✧٩(ˊωˋ*)و✧